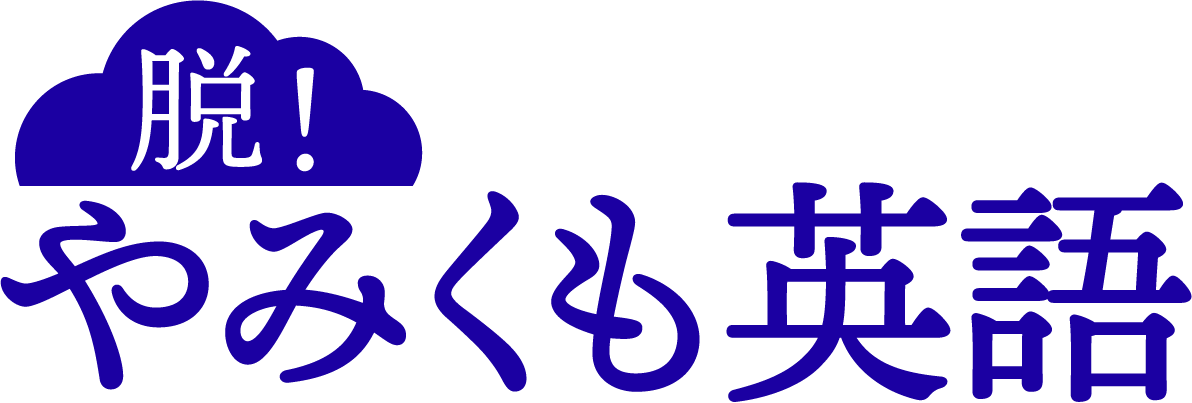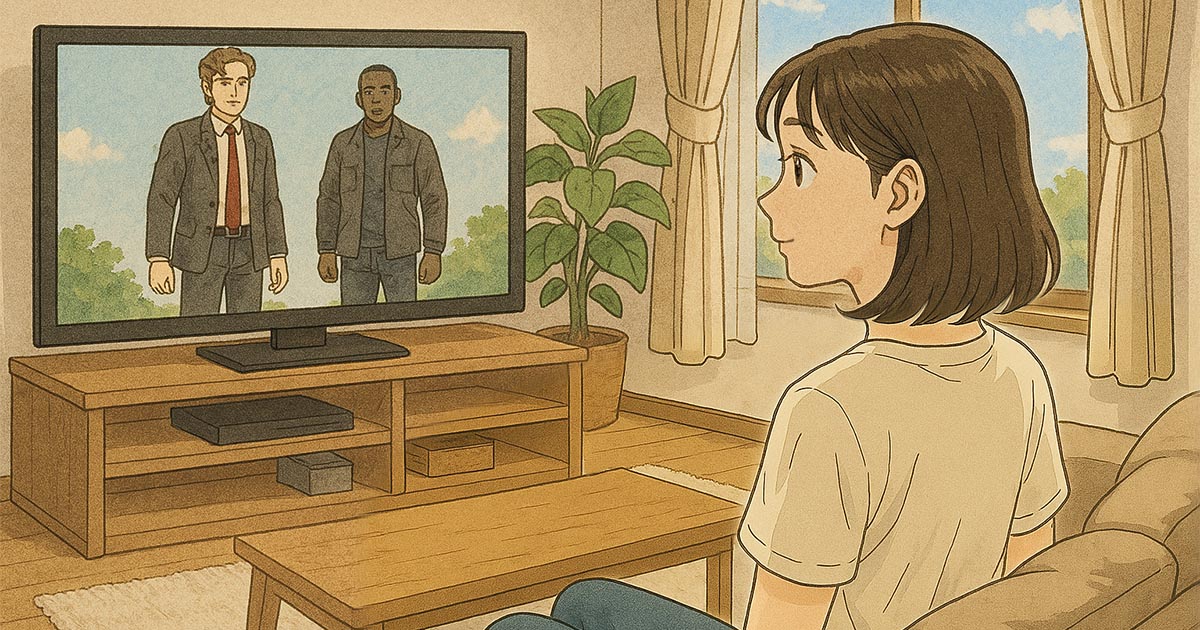
「機械的」と「有機的」
日本の英語学習では、「機械的」なやり方が主流になっています。
それに対するのは、「有機的」な学び方です。
この2つの言葉は、英語でも "mechanical learning" と "organic learning" という形で使われており、学び方の違いをよく表しています。
機械的な学習 (Mechanical Learning)
特徴:
- 単語や文法を暗記する
- 反復練習やテスト形式で覚える
- 文脈や実生活から切り離して学ぶ
- 手順やルールに従って進める
例:
- 単語帳による暗記に偏り、文脈や使われ方を軽視する
- 文法項目ごとに選択問題や穴埋め問題を大量にこなす
- 音声を何度も聞き流して、意味や文法を考えずに覚えようとする
- 試験対策として出題パターンを分析し、それを覚える
- 過去問や模試を答え合わせだけして、ミスを機械的に修正する
有機的な学習 (Organic Learning)
特徴:
- 自然な流れの中で学ぶ
- 文脈や実生活の中で意味を理解する
- 体験やコミュニケーションを通して言葉を身につける
- 全体を把握し、つながりを意識して学ぶ
例:
- 好きな本を英語で読む
- 英語で日記やメールを書く
- 映画やドラマで英語に触れる
- 英語で会話しながら覚えていく
- 興味のあるテーマを英語で調べてみる
私が強く勧めているのは、後者の有機的な学び方ですが、英語学習の世界には、機械的な方法論があふれています。
その中で、自分の声がかき消されてしまうようなもどかしさを感じることもあります。
日本のインプット中心教育
先日、ある英語ネイティブと話をしていて、こんな言葉が印象に残りました。
「日本の教育は、国語も含めてインプット中心なんだよね」と。
つまり、読み取りや聞き取りは重視されても、アウトプット――つまり自分の言葉で考えや気持ちを表現することが、あまり重視されていないのではないか、と。
たとえば国語のテストでは、自分の意見を書く小論文形式ではなく、出題者や作者の意図を選択肢から選ぶ問題が多いですよね。
受験対策も含め、日本の学校教育は「機械的な学習」を前提としているように見えます。
そういった教育を受けてきた私たちが、社会人になってからも同じようなやり方で何かを学ぼうとするのは、ある意味当然なのかもしれません。
もちろん、漢字の学習のように、機械的な反復が必要な場面もあります。
機械的な学習がすべて悪いわけではありません。
でも、今の教育はあまりにもその比重が大きすぎるのです。
「有機的」かつ「体系的」がポイント
私は、受験勉強にはあまり熱心ではありませんでした。
どちらかというと「学ぶこと自体を楽しみたい」タイプだったと思います。
そして偶然にも、英語圏で年単位の教育を受ける経験がありました。
そのおかげで、日本の高等教育を経験しつつも、外から俯瞰して考える視点を持つことができたと感じています。
私はよく「英語を"言葉"として学ぼう」と言っています。
そう言うと、「じゃあ、体系的に学ばなくていいんだね」「経験だけで身につければいいんだね」と、極端に捉える人もいます。
もちろん、そんなことはありません。
大人の脳は子どもとは違い、自然に言語を吸収する力には限界があります。
だからこそ、大人が有機的に学ぼうとするなら、まとまって整理された知識として、つまり体系的に学ぶ必要があるのです。
必要なのは、「有機的に」「体系的に」学ぶこと。
両方をバランスよく組み合わせることが、大人の英語学習には不可欠です。
「じゃあ、どうやって“有機的に、体系的に”学べばいいの?」
そう疑問に思う方もいるかもしれません。
先ほど挙げた「有機的学習の例」を見れば、ある程度イメージはできるはずです。
ただ、それだけでは足りないので、基礎学習や4技能学習などの体系的な学習が必要になります。
それでも「最短ルート」や「攻略法」を求めてしまうなら、その感覚こそが、機械的な学習に慣れてしまっている証なのかもしれません。