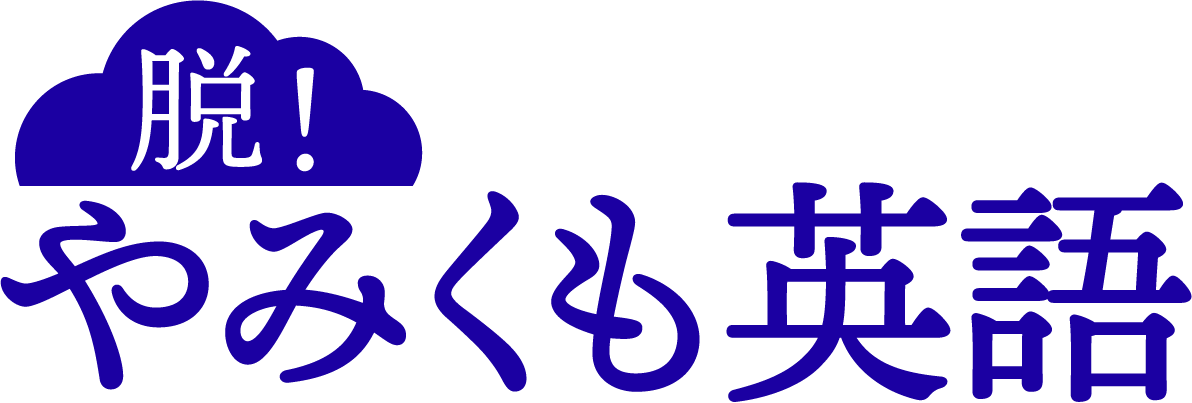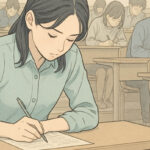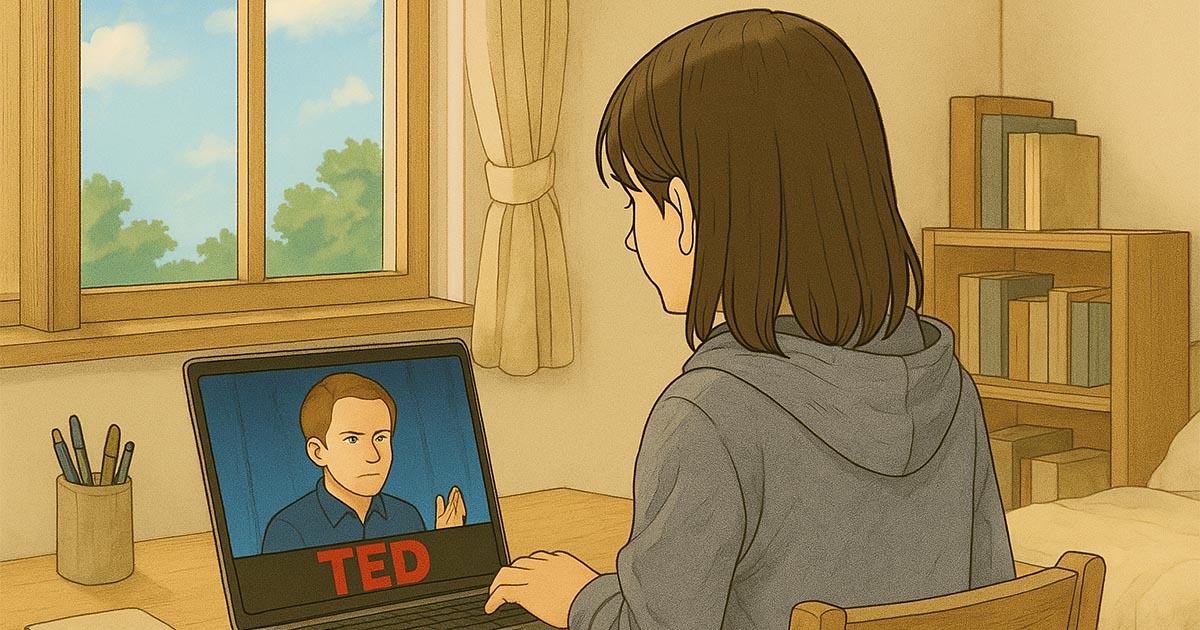
英語学習のブランクと発音の復習
私は、去年まで長いあいだ英語学習のブランクがあり、今年になって、ようやく発音の復習を始めました。
これまで私は電子辞書で、学び始めの頃はジーニアス英和辞典、少し慣れてきた頃からはジーニアス大英和辞典をずっと使ってきました。
わからないことはすべて辞書をきちんと引いてきたつもりなので、そこに載っている発音記号を頼りに、長年それなりに発音を学んできたつもりでした。
発音学習での模索
IPAとの出会い
でも、国際音声記号(IPA)という存在は、正直ほとんど意識したことがありませんでした。
ブランク中に耳にしたことはあったかもしれませんが、当時は英語を学ぶ余裕がなく、そのまま流してしまったのだと思います。
でも、発音をやろうとすると、必ずIPAという言葉が出てくるので、これは学ばなくてはならないと思うようになりました。
そして、今年になってから、ブランク中に「そのうち読もう」と思って買っておいた発音記号の本を読んでみました。
……が、全然ピンとこない。どれも一応知ってる感じ。
さらに、ジーニアスで見慣れている発音記号とIPAとの違いもよくわからず、調べても大きな違いはないとわかったので、「もう理解できている気がするけれど…?」と思ってしまっていました。
Duolingoでは足りなかった発音練習
それでも、フランス語学習のために使い始めたDuolingoで、ついでに英語の発音も練習してみたり、いろいろ試してみました。
でもDuolingoは、幅広い発音を受け入れる設計になっているのか、かなり適当な発音でもOKが出てしまいます。
そのため、発音の練習にはなりませんでした。
BoldVoiceとの出会いで変わったこと
そんなときに出会ったのが、BoldVoiceというアプリです。
このアプリで、ようやく「自分の発音の何が悪いのか」が具体的に見えるようになりました。
それと同時に、今まであまり意味がわからなかった発音の本も、実感をもって読めるようになっていきました。
BoldVoiceでは、男性と女性の専門家がそれぞれ動画で発音をデモンストレーションしてくれて、うまく発音できなかった音については、専用の解説動画が表示されます。
アプリ自体のチェックもかなり厳しく、「アプリの不具合なんじゃないの?」と思うくらい、どうしても合格しない音が出てくることもあります。
やっぱり、写真と文字の解説、CD音源だけでは限界があったんだなと改めて感じました。
私には、動きと音をリンクさせて理解する必要がありましたし、リアルタイムのフィードバックも必要だったのです。
TEDスピーチの練習で感じたショック
ただその後、それまで練習していたTEDスピーチのスクリプトを声に出すのが、少し怖くなってしまいました。
なぜなら、自分の発音が、実はとてもいい加減だったことに気づいてしまったからです。
私は去年からネイティブの先生についていますが、人が相手だとどうしても寛容になってしまうのか、発音チェックを頼んでも、実際にはあまり細かく修正されないまま来てしまいました。
試しにTEDのスクリプトにすべてIPAの発音記号をつけてみたのですが、アプリでまだ習得しきれていない音も多く、自信を持って口に出せる単語が、実は少なかったことにも気づきました。
また、このアプリには、単語だけでなく、センテンス単位での発音チェック機能もあります。
単語ならそれなりに発音できても、文章になると途端に崩れてしまい、自分でもショックを受けました。
その結果、アプリレベルのチェックのない状態でTEDスピーチを読むのは、今の私にはあまり理想的ではないと感じました。
自分では「発音できている」と思っていても、実際にはできていない音が多く含まれていたからです。
BoldVoiceには、自分で文章を入力して練習できる機能もありますが、TEDのスクリプトを使ってそれを試してみたところ、やはりできていない発音が多くありました。
訛りの範囲内
通じているけど、不自然
もちろん、TEDスピーチを暗唱する練習自体は、今でもとても有意義だったと思っています。
私の発音がそのままでも、おそらく多くの英語学習者には通用したかもしれません。
実際、私の発音はネイティブの先生や友人たちには、きちんと通じていました。
それで今になって思うのは、きっと「訛りの範囲内」として処理されていたのだろうということです。
たとえば、外国人が話す日本語が、イントネーションがおかしくても、私たちには意味が伝わるように——「通じはするけれど、日本語としては不自然」な、あの感覚に近かったのではないかと思います。
つまり、自分では通じているつもりでも、実際には「きちんとした音」になっていなかった可能性がある。
そう思うようになってから、発音をやり直すことの意義が、はっきりと見えてきました。
訛りとリスニング力
もちろん、「訛りを直す必要はない」という考え方もあります。
でも、TEDスピーチを使った練習では、自分が理解できる内容で、なおかつ発音を意識しながら聞いたり暗唱したりすることで、私のリスニング力は明らかに向上しました。
それでも、私のリスニング力は、ネイティブレベルとはほど遠いものです。
だから私は、自分の今の発音が、自分の今のリスニング力を表しているのだと思い始めました。
また、訛りと間違いの区別は非常に微妙なところだと思います。
なぜなら、日本人にとって全て「ア」に聞こえる音でも、英語話者にとっては全く違う音であり、その音1つが違うだけで違う単語になってしまう場合があるからです。
逆に、その違いがあまり単語の識別に影響を与えない時もあります。
そのため、自分の解釈で「これは訛りだから、個性として残して良い」と判断するのが難しい部分もありますので、できるだけ正確に発音するのが最善なのではないかと個人的には思います。
私は最終的にはネイティブレベルを目指しているので、この訛りをできるかぎり直しながら、リスニング力を高めていきたいと思います。
英単語は「漢字」と同じだった
私は実は中国語も学んでいたことがあります。
そこでふと、「英語の発音記号は、もしかしたら中国語のピンインと同じなのでは?」と考えるようになりました。
中国語は漢字の言語で、もともとはふりがなのような表記がありませんでした。
だから、ピンインがなければ、外国人は読むことすらできません。
中国語学習者にとって、ピンインは“読み方を見える化するツール”です。
そして、それと同じように、英語にとってのIPAも“音を見える化するツール”なのだと、ピンインを通してようやく実感しました。
だって英語も、書いてある通りに読めるわけじゃありません。
スペルと読み方が全然違うのですから、まるで“漢字”のようではありませんか?
本気で発音を学び始めたからこそ、ようやくこのことに気づくことができました。
これは、私の長年の学習の中で、「英語は構造の言語である」という(それなりに知られた)事実に次いで、いちばん大きな気づきだったかもしれません。
“ふりがな”とその基準
“ふりがな”を振れるようにしておく
中国語では、ピンインはすべての漢字に対応させて書けるようにするべきだとされています。
日本語のふりがなも同じです。※
つまり、基本的に英単語にも発音記号を書けるようにしておくべきだと、個人的には強く思うようになりました。
発音の基準
ここで出てくるのが、「発音の基準をどうするか」という問題です。
文化的な議論はさておき、まずはジェネラル・アメリカン(GA)とレシーブド・プロナンシエーション(RP)のどちらかを選ぶ、という形で良いのではないかと思います。
BoldVoiceは、GAではなく、ハリウッド発音に基づいているらしいのですが、私はカリフォルニアに留学していたこともあり、とりあえずこのアプリを1年間使ってみることにしました。
なお、BoldVoiceはまだ日本語化が途中で、専門家の説明は字幕も含めてすべて英語です。
(一部のナビゲーションだけが日本語になっていますが、かなり修正が必要なクオリティです。)
そのため、ある程度の英語力がないと、このアプリを使いこなすのは難しいかもしれません。
他にも良いアプリが見つかったら、またご紹介したいと思います。
※ひらがなやピンインでも文字の通りに音が表されているわけではありませんが、ここではわかりやすさのために発音記号と同じような扱いにさせていただきました。